強制ライセンス:特許を公共の利益のために上書きする法的手段

- 三浦 梨沙
- 21 11月 2025
- 12 コメント
特許は、新しい発明を一定期間独占的に使えるようにする制度です。でも、その独占権が命を救う薬の価格を高騰させ、多くの人が手に入れられなくなるとき、どうすればいいでしょうか?強制ライセンスは、そのような状況で政府が特許権者に無断で第三者に製造・使用を許可する、法的な手段です。これは、特許の独占を一時的に制限して、公共の健康や緊急事態に対応するための仕組みです。
強制ライセンスとは何か?
強制ライセンスは、特許権者が同意しなくても、政府が法律に基づいて他の企業や団体に特許技術の使用を許す制度です。ただし、特許権者には「適切な報酬」が支払われなければなりません。これは「特許の独占」を否定するのではなく、その独占が社会に大きな被害を及ぼすとき、公共の利益を優先させるための調整弁です。
この制度は、1883年のパリ条約で初めて国際的に認められ、1994年のTRIPS協定(知的財産の貿易関連の側面に関する協定)で世界共通のルールが整備されました。TRIPS協定では、強制ライセンスを発行するには、まず特許権者と交渉する努力が必要とされています。ただし、パンデミックや国家非常事態のような「極度の緊急事態」では、この交渉の手順を省略できます。
なぜ必要なのか?薬の価格と命の問題
強制ライセンスの最も顕著な使用例は、薬品です。HIV治療薬やがんの薬は、特許を持っている製薬会社が高価格を維持すると、低所得国ではほとんど手に入れられません。2001年、ブラジルはエファビレンツというHIV薬の強制ライセンスを発行。価格は1錠1.55ドルから0.48ドルに下がりました。タイでは、ロピナビル/リトナビルの価格が年間1200ドルから230ドルに、エファビレンツは550ドルから200ドルに下がりました。
世界保健機関(WHO)のデータによると、2000年から2020年の間に、低・中所得国でのHIVの第一選択薬の価格は92%下がりました。その背景には、強制ライセンスの存在が大きく影響しています。特許権者が「価格を下げないなら、国がライセンスを発行する」という脅しをかけるだけで、多くの製薬会社が自発的に価格を引き下げたのです。研究によると、この脅しによって、2000年以降、開発途上国のHIV薬の90%で価格交渉が成功しています。
国ごとの違い:アメリカ、インド、ドイツ
強制ライセンスの使い方は国によって大きく異なります。
アメリカは、非常に慎重な国です。1945年から2020年まで、政府が使用するための強制ライセンスはわずか10件しか発行されていません。主に軍事や政府機関が使う技術に対して使われ、医薬品ではほとんど使われません。ただし、連邦政府が補助金を出して開発した薬(バイ・ドール法)に対しては、製薬会社が「実用化を怠っている」と判断されれば、政府が強制ライセンスを発行できる「マーチ・イン権」があります。しかし、これまで12件の申請がありましたが、1件も許可されていません。
一方、インドは世界で最も積極的な国です。2005年以降、22件の強制ライセンスを発行。そのほとんどががん治療薬です。2012年、インドはドイツのバイエル社の腎がん薬「ネクサバー」に対して強制ライセンスを発行。価格は月額28万円から約5000円に下がりました。バイエルは訴訟を起こしましたが、8年後にインドの裁判所は強制ライセンスを維持する判決を下しました。
ドイツは法律上、公共の利益のために強制ライセンスを発行できる仕組みがありますが、実際には一度も発行したことがありません。一方、スペインは2020年、新型コロナウイルスの治療薬やワクチンに対して、交渉を省略して強制ライセンスを発行できる法令を急遽制定しました。

実際の手続きはどうなる?
強制ライセンスを申請するには、いくつかのステップを踏む必要があります。
- まず、特許権者と交渉する(緊急時を除く)
- 公共の健康や国家非常事態であることを証明する
- 国内で生産・供給できる能力があることを示す
- 政府がライセンスを発行し、報酬の額を決定
報酬の額の決め方は国によって違います。アメリカでは、過去の類似ライセンスの使用料や、技術の価値、市場規模など15の要素を総合的に判断する「ジョージア・パシフィック基準」を使います。インドでは、製品の純売上高の6%を報酬とするルールが定められています。
手続きの期間も異なります。インドでは、申請から決定まで18〜24か月かかります。アメリカでは、連邦裁判所で訴訟を起こし、平均2.7年かかります。一方、スペインの2020年の措置のように、緊急時には数週間で発行できる仕組みもあります。
賛成と反対の声
強制ライセンスをめぐっては、激しい議論があります。
賛成派は、命を救うための不可欠な手段だと主張します。エレン・ト・ホーン博士は、「パンデミックのとき、交渉の時間なんてない。法律は、人命を守るためにあるべきだ」と言います。また、ジョン・L・コントラス教授の研究では、強制ライセンスが発行されたケースの83%で、薬価が65〜90%下がったことが確認されています。
反対派は、イノベーションを阻害すると警戒します。国際製薬工業協会(IFPMA)は、強制ライセンスが発表された直後に、関連企業の株価が平均8.2%下落したと報告しています。2018年の研究では、強制ライセンスを頻繁に使う国では、製薬企業の研究開発投資が15〜20%減ったというデータもあります。
しかし、この懸念は「過剰な使用」が問題なのであって、適切な使用は逆に市場を活性化させます。たとえば、インドの強制ライセンスによって、ジェネリック薬メーカーのテバ社は2015年から2020年までに32億ドルの追加収益を上げました。これは、低価格薬の需要を生み出し、製薬業界全体の市場を広げた結果です。

最新の動向:パンデミックと未来
2022年、世界貿易機関(WTO)は、新型コロナワクチンの特許を一時的に無効にする「暫定免除」を承認しました。開発途上国がワクチンを自国で生産できるようにするための措置です。しかし、実際に利用している国はわずか8カ国、12施設にとどまっています。理由は、技術移転の難しさや、国際的な圧力です。
EUは2023年、医薬品戦略で「緊急時に製薬会社は30日以内にライセンスを提示しなければ、強制ライセンスを発行する」という新ルールを提案しました。これは、交渉の壁をさらに低くする動きです。
WHOは現在、今後のパンデミックに備えて「パンデミック条約」の交渉を進めており、その草案には「WHOが国際的公衆衛生上の緊急事態と宣言した場合、必要な医療品は自動的にライセンスが発行される」という条項が含まれています。
日本はどうすべきか?
日本は、強制ライセンスの法律を持っていますが、これまで一度も使ったことがありません。医薬品の価格は、薬価制度や保険制度でコントロールされているため、強制ライセンスの必要性を感じていないのが実情です。
しかし、今後、新薬の価格が高騰し、医療費の負担が限界に達したとき、あるいは次の大規模な感染症が発生したとき、この制度が「使えない」状態でいるのは危険です。強制ライセンスは、決して「特許を奪う」道具ではありません。それは、市場の失敗を修正し、命を守るための最後の手段です。
日本は、法律の整備だけでなく、専門家チームを常設し、緊急時に即座に対応できる体制を整えるべきです。技術的な知識、法的判断、価格交渉の経験--これらは数年で身につくものではありません。今から準備を始めなければ、次の危機で取り残されます。
強制ライセンスは特許を奪う行為ですか?
いいえ、特許を奪うわけではありません。特許権者はその技術の使用を許可されませんが、その見返りとして「適切な報酬」を受け取る権利は保証されます。これは、独占権の一部を一時的に制限するだけの仕組みです。
日本で強制ライセンスは使えるのですか?
はい、日本にも特許法に基づく強制ライセンスの制度はあります。しかし、これまで一度も発行されたことはありません。理由は、薬価制度や保険制度で価格をコントロールできるとされてきたためです。ただし、今後、緊急事態や価格暴騰が起きた場合、使用の可能性は十分にあります。
強制ライセンスは医薬品以外にも使われますか?
はい、農業用農薬、環境技術、エコ製品、視覚障害者向けの書籍など、さまざまな分野で使われています。2017年のマラケシュ条約では、視覚障害者向けのコンテンツの複製を許可する強制ライセンスが154カ国で導入されました。
強制ライセンスの発行は国際的な報復を招きますか?
過去には、アメリカが「特別301報告書」で強制ライセンスを発行した国を「監視対象国」に挙げたことがあります。しかし、実際の経済制裁や貿易制裁は2012年以降行われていません。国際的なルール(TRIPS協定)の中で、強制ライセンスは合法と認められているため、単なる政治的圧力にとどまっています。
強制ライセンスはイノベーションを止めてしまうのでは?
一部の研究では、強制ライセンスが頻繁に使われる国では、製薬会社のR&D投資が減る傾向があると報告されています。しかし、その影響は「過剰な使用」に限られます。実際には、強制ライセンスの「脅し」が、製薬会社に自発的な価格引き下げを促す効果が大きく、結果として市場全体のアクセスを広げています。バランスが重要です。


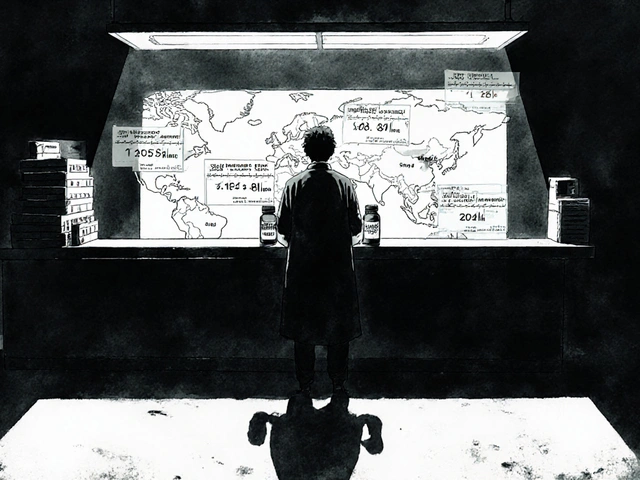
コメント
利音 西村
またか…また国が企業を脅す話か?これで製薬会社が日本から撤退したらどうすんの????????????
11月 23, 2025 AT 02:37
TAKAKO MINETOMA
強制ライセンスって、実は『脅し』として機能してる部分が一番大事なんですよね。製薬会社が『あ、こいつら本気だ』って気づいて、価格を下げ始める。インドのケース、本当に凄い。でも、日本は『保険でカバーできるから大丈夫』って、まるで地震が来ても『避難訓練は必要ない』って言ってるようなもん。準備してないと、次は本当に手遅れになるよ。
11月 24, 2025 AT 07:08
kazunari kayahara
日本は法律あるのに使わないって、まるで防災訓練だけして本物の災害には備えないみたいなもんよね。それとも、『高価な薬は貧乏人が死ぬ分にはいい』って暗黙のルールでもあるの?😅
11月 24, 2025 AT 12:04
JUNKO SURUGA
インドのケース、本当に感動した。あの価格差、命の差だよね。日本も、もう少し現実を見たほうがいい。
11月 24, 2025 AT 17:55
優也 坂本
お前ら、ただの感情論で語ってるだろ?R&D投資が15〜20%減るってデータは無視?製薬業界は『科学の聖域』だ。強制ライセンスは『科学の盗賊行為』だ。アメリカが監視対象に挙げたのは、単なる政治的圧力じゃない。『イノベーションの根幹』を守るために必要な警戒だ。
11月 26, 2025 AT 04:09
Ryota Yamakami
でもね、インドでジェネリックが広まって、むしろ世界の薬価が下がって、結果的に製薬会社の売上も伸びたって話もあるんだよ。『奪う』じゃなくて『広げる』って考え方もあると思う。
11月 27, 2025 AT 11:00
門間 優太
確かに、インドの成功例は参考になる。でも、日本は『価格交渉』で対応してきたから、制度がなくても問題なかった。これからもそのやり方でいいんじゃない?
11月 27, 2025 AT 14:34
yuki y
強制ライセンスってなんか怖いイメージだけど実際は命を救うための仕組みなのかな?ちょっと勉強してみたけど、なんかすごいなって思った!
11月 29, 2025 AT 01:53
Hideki Kamiya
ほら、また国が『世界の陰謀』に屈してる。製薬会社はアメリカのCIAと繋がってるって噂もあるぞ?強制ライセンスって、実はグローバリズムの道具なんだよ。日本はアメリカの言いなりになるな!🚀
11月 30, 2025 AT 15:26
Keiko Suzuki
強制ライセンスは、特許制度の『安全弁』です。制度があるだけで、製薬会社は価格を引き下げるインセンティブが生まれます。日本は、この『安全弁』を、いざという時に使えるように、専門チームを常設すべきです。
11月 30, 2025 AT 15:47
花田 一樹
日本は『使わない』のが正解だって思ってるけど、それって『火災報知機を外す』のと同じ。使わないから安全ってわけじゃない。火事は、『いつ来るか』じゃなくて『いつまでに準備するか』だ。
12月 2, 2025 AT 03:36
EFFENDI MOHD YUSNI
TRIPS協定の例外条項を悪用する国々は、知的財産の国際秩序を破壊している。強制ライセンスの濫用は、グローバルな医療イノベーションの崩壊を招く。このままでは、次世代の新薬は『開発不可能』になる。これは単なる政策論ではない。文明の存亡に関わる問題だ。
12月 2, 2025 AT 16:24