ジゴキシン(Digoxin)とは?作用機序・適応・副作用・飲み方ガイド【2025年最新版】

- 三浦 梨沙
- 30 8月 2025
- 5 コメント
鼓動がバラつく、息が上がる、脈が遅すぎる。そんなときに昔から頼られてきた一錠がある。ジゴキシン。長く使われてきた分、効き方も落とし穴もはっきりしている薬。ここでは「何に効くの? どう飲めば安全? どこまでがセーフ?」を、実際に生活の中で役立つ形でまとめる。期待できる効果はあるけれど、自己判断は危険。今日読んで、明日の通院で医師・薬剤師に要点を確認できるレベルまで持っていこう。
- TL;DR:心房細動の心拍コントロールや、左室収縮不全の息切れ緩和に使うが、第一選択ではない場面が増えている(AHA/ACC/HFSA 2022、ESC 2023)。
- 安全のコアは「腎機能・電解質・血中濃度(0.5-0.9 ng/mL目安)」の3点管理。採血は最終服用6-8時間後が基本(PMDA添付文書)。
- アミオダロン、ベラパミル、クラリスロマイシン、キニジンなどは血中濃度を上げやすい。多くは減量+濃度チェックが必要。
- 吐き気、食欲低下、視覚異常(黄色っぽく見える)、極端な徐脈・不整脈は要受診。急性中毒は119と救急へ。特効薬はジギ毒素抗体Fab。
- 高齢・やせ型・腎機能低下・利尿薬併用は要リスク管理。スタートは低用量(62.5-125 µg/日)が鉄則。
ジゴキシンの基本:何に効く?どう効く?(2025アップデート)
ジゴキシンは、強心配糖体。大きく2つの顔がある。
- 心房細動(AF)・心房粗動の心拍コントロール:房室結節の電気伝導を抑えて、脈を落ち着かせる。安静時には効きやすいが、運動時の心拍コントロールは弱い(ESC 2023 AFガイドライン)。
- 左室収縮不全(HFrEF)の症状軽減:入院を減らすエビデンスがあるが、死亡率は下げない(DIG試験、Cochrane 2014)。今はARNI、β遮断薬、MRA、SGLT2阻害薬が土台。上乗せで検討する位置づけ(AHA/ACC/HFSA 2022)。
作用機序はシンプルで強力。Na⁺/K⁺-ATPaseを阻害→細胞内Na⁺上昇→Na⁺/Ca²⁺交換が抑えられ、細胞内Ca²⁺が増えて収縮が強まる。一方で迷走神経トーンが上がり、房室結節の伝導を抑える。だから「収縮を助け、脈を落ち着ける」。
ただし「効く=安全」ではない。治療域が狭い(therapeutic window)。0.5-0.9 ng/mLくらいで十分な効果が出て、中毒がグッと減ることが分かってきた(AHA/ACC/HFSA 2022、PMDA添付文書)。
大阪でも外来での新規開始は昔より少ない印象。理由は、腎機能や併用薬の影響を強く受けるから。だからこそ、飲むなら「見える化」=検査とサインのチェックが命綱になる。
安全に使うための実践ステップ(用量・採血・相互作用・日常のコツ)
ここからは、実際に役立つ手順に落とす。病院での方針が最優先。これは準備と確認のメモとして使ってほしい。
1)始める前にそろえる検査と情報
- 腎機能:eGFR/クレアチニン。腎で主に排泄される。
- 電解質:K、Mg、Ca。低K・低Mg・高Caは中毒を呼ぶ。
- 心電図:徐脈・房室ブロックの有無。
- 体重・体格:やせ型・高齢女性は感受性が高い。
- 併用薬リスト:処方・市販薬・サプリ・健康茶を全部。とくにP-gp阻害薬/誘導薬は要注意。
2)用量の考え方(目安)
- 一般成人の維持量:0.125-0.25 mg/日(125-250 µg)。
- 高齢・やせ型・腎機能低下:62.5-125 µg/日、または隔日投与から。
- 入院下のAFで速すぎる脈を落とす時に限って、負荷投与(例:合計0.75-1.0 mg分割)を検討することがある。外来の自己判断では絶対にやらない。
「とりあえず半錠で様子見」は危険。目安はあくまで目安。必ず担当医の指示で。
3)飲み方と採血のタイミング
- 1日1回、毎日同じ時間に。食後でOK。食物繊維サプリや小麦ふすまは吸収を落とすので、2時間以上ずらす。
- 制酸薬、コレスチラミン、カオリン・ペクチンは吸収を下げる。こちらも2-6時間離す。
- 血中濃度の採血は、最終服用から6-8時間後(理想はトラフ=次回服用直前)。開始・増量後1-2週間で一度チェック。
4)相互作用:覚えておく「赤札」リスト
- 濃度が上がる(要減量+濃度確認):アミオダロン、ドロネダロン、ベラパミル、ジルチアゼム、マクロライド(クラリスロマイシン、エリスロマイシン)、アゾール系(イトラコナゾール等)、キニジン、シクロスポリン、タクロリムス、リトナビル/コビシスタットなど。
- 濃度が下がる(効きにくい):リファンピン、セントジョーンズワート(セイヨウオトギリソウ)。
- 中毒を招く間接要因:ループ利尿薬・サイアザイド(低K・低Mg)、下痢・嘔吐・脱水。
アミオダロンを開始したら、ジゴキシンは通常半量に。3-5日で濃度を一度確認。こういう「運用ルール」を処方箋の備考やお薬手帳に書いておくと安心。
5)中毒サイン(見逃さない合図)
- 胃腸:吐き気、嘔吐、食欲低下、お腹の違和感。
- 神経:めまい、混乱、倦怠感。
- 視覚:黄色っぽく見える、かすむ、光がにじむ。
- 心臓:極端な遅い脈、脈が飛ぶ、胸の不快、失神。
思い当たる症状+新たな薬の開始、夏の脱水、胃腸炎。この組み合わせは危ない。強い症状があれば119。救急ではジギ毒素抗体Fab(抗体製剤)が使われる(PMDA、救急医療の実務)。
6)日常のコツ(大阪の夏は要注意)
- 水分・塩分バランス:利尿薬併用なら特に、猛暑日はスポーツドリンクより経口補水液寄りで。
- 風邪や胃腸炎のとき:無理せず早めに主治医へ。下痢・嘔吐は中毒の引き金。
- お酒:大量摂取で脱水→中毒リスク上がる。ほどほどに。
私は外来で、夏に「食欲ゼロ+利尿薬+ジゴキシン」の人を何度も見てきた。こんな時は一人で抱え込まないのがいちばんの安全策。

よくあるシナリオと判断のコツ(ケースで学ぶ意思決定)
ケースA:安静時の脈は落ちたけど、歩くとすぐ速くなる(AF)
ジゴキシンは運動時の心拍コントロールが弱い。β遮断薬や非DHP系Ca拮抗薬(ベラパミル/ジルチアゼム)を優先・併用検討がガイドラインの流れ(ESC 2023)。併用時は相互作用で濃度が上がるので、ジゴキシンを減量して濃度チェック。
ケースB:eGFR 28、やせ型、高齢女性。どこから始める?
62.5 µg/日か隔日投与から。1-2週間で濃度と電解質を確認。Kは4.0-5.0 mEq/L、Mgは2.0 mg/dL以上をキープ。利尿薬調整も同時に。
ケースC:アミオダロンを開始した(VT既往)。どうする?
ジゴキシンは半量へ。3-5日後に濃度を採る。脈が遅すぎないか、めまいはないかを自己モニター。お薬手帳には開始日と次回採血予定を書いておく。
ケースD:朝飲み忘れた! 夜気づいた
気づいた時刻が次の服用時間に近ければスキップ。2回分をまとめて飲まない。次回から通常通り。自己判断で余分に飲むと危ない(PMDA添付文書)。
ケースE:妊娠・授乳
妊娠中も必要なら使われる。胎児SVT治療でも用いられることがある。授乳中は母乳移行はわずかで多くの指針で「授乳可」だが、乳児の哺乳力低下や徐脈がないかは一応観察(LactMed 2024、日本小児科学会資料)。
ケースF:ECGで“スコップ様ST低下”。中毒?
いわゆる"digoxin effect"で、中毒ではなく薬理作用による変化。症状と濃度で評価。症状がなく、濃度が目標域なら慌てない。
ケースG:大阪の猛暑でフラつき、食欲なし
脱水+低K・低Mgが疑わしい。自己中断はせず、早めに医療機関へ。状況によっては一時的に休薬・補液・電解質補正・濃度測定。
チートシート・表・FAQ・次の一歩
数字でわかるジゴキシン(保存版)
| 項目 | 目安・数値 | メモ |
|---|---|---|
| 血中濃度(HF) | 0.5-0.9 ng/mL | これで十分なことが多い(AHA/ACC/HFSA 2022) |
| 血中濃度(AF) | 明確な目標はないが2.0 ng/mL超は危険域 | 症状・脈と併せて判断 |
| 採血タイミング | 最終服用6-8時間後 | トラフが理想 |
| 半減期 | 36-48時間 | 腎機能低下で数日に延長 |
| 主な排泄 | 腎(50-70%) | eGFRに応じて調整 |
| 維持量(成人) | 0.125-0.25 mg/日 | 高齢・腎障害は低用量 |
| 高齢・腎障害 | 62.5-125 µg/日 or 隔日 | 開始時は攻めない |
| 内服後発現 | 30-120分 | 完全な定常状態は数日後 |
| 相互作用(↑濃度) | アミオダロン、ベラパミル等 | 減量+濃度チェック |
| 特効薬 | ジギ毒素抗体Fab | 重症中毒時に使用 |
チェックリスト(印刷OK)
開始前チェック
- eGFR、K、Mg、Ca、ECGを確認した
- 併用薬の相互作用を確認した(特にアミオダロン、マクロライド)
- 開始量は低めでスタートする計画
- 採血タイミング(6-8時間後)と再診日を決めた
毎日のセルフチェック
- 脈が極端に遅くないか(例:50/分未満+症状)
- 吐き気・食欲低下・視覚異常が出ていないか
- 脱水になっていないか(猛暑・下痢・嘔吐)
NGになりやすい組み合わせ
- ジゴキシン+アミオダロン(要減量)
- ジゴキシン+利尿薬+夏の脱水(中毒の温床)
- ジゴキシン+クラリスロマイシン(代替抗菌薬を検討)
ミニFAQ
- Q:運動しても大丈夫?
A:OK。ただしAFの心拍コントロールは運動時に効きにくい。動悸が強いならβ遮断薬などでの調整を主治医に相談。 - Q:コーヒーやお茶は?
A:適量ならOK。利尿で脱水しない範囲で。 - Q:グレープフルーツは?
A:大きな影響は少ないとされるが、相互作用の塊みたいな体質の人もいる。飲み始めに濃度を見ておくと安心。 - Q:漢方・健康茶は?
A:甘草(カンゾウ)は低K→中毒リスク。セントジョーンズワートは濃度低下。必ず申告を。 - Q:どれくらいの期間飲む?
A:疾患と反応次第。AFの心拍コントロールやHFrEF症状緩和で長期になることも。定期的に「本当に必要?」を見直す。 - Q:やめる時は?
A:自己中断はNG。徐々に調整、他剤へリレーすることがある。 - Q:在宅で血圧計しかない。どう役立てる?
A:脈拍表示を毎回メモ。50台でふらつく、100超が続く、リズムが乱れすぎるなら受診の目安。
次の一歩/トラブルシューティング
あなたの状況に合わせて、今日からできる行動を並べる。
- 新規処方が出た:開始量、採血予定日、相互作用の有無(特にアミオダロン・マクロライド)をその場で確認。お薬手帳に「次回濃度採血○/○(6-8時間後)」と記入。
- 夏バテで食べられない:利尿薬の量、補水、電解質を主治医に早めに相談。中毒サインがあれば受診を先延ばししない。
- 別の医療機関で抗菌薬が出た:薬局で相互作用をその場チェック。「ジゴキシン服用中」と伝えるだけで事故が減る。
- 在宅で脈が遅すぎる・ふらつき:一旦安静、転倒注意。症状があれば受診。意識が遠のく、胸痛・失神は119。
- 濃度が1.8 ng/mLだった:症状と腎機能、併用薬を総合で判断。目標は0.5-0.9 ng/mL(HF)。減量や間隔調整、相互作用の見直し。
根拠の出どころ:PMDA添付文書(2025時点)、AHA/ACC/HFSA心不全ガイドライン(2022)、ESC心房細動ガイドライン(2023)、Cochraneレビュー(2014)、LactMed(2024)。現場の運用は施設で微調整が入る。疑問は遠慮なく、次回診察で3つだけ質問を用意して聞こう。「目標濃度は?」「次の採血は?」「相互作用はある?」--この3つで安全度は一気に上がる。


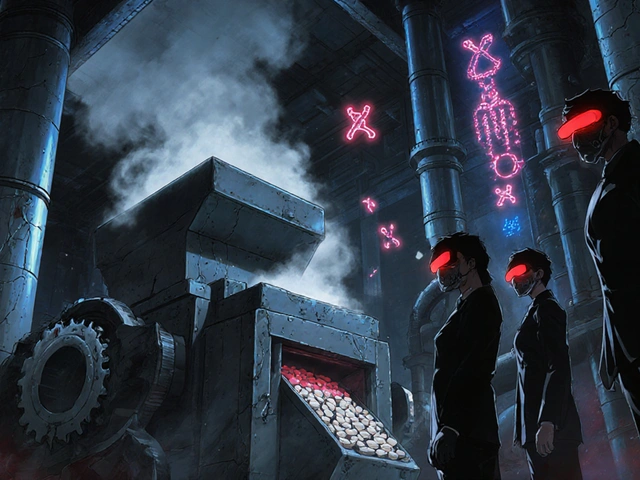
コメント
HIROMI MIZUNO
この記事めっちゃ役立った!特に夏の脱水とジゴキシンの組み合わせ、本当に怖いよね
私の祖母も利尿薬と併用してて、去年の猛暑で具合悪くして救急搬送されたんだ
それから毎日脈を測って、お薬手帳に「今日の脈:58」「水分:1.5L」って書いてる
医者に「ちゃんと見てるの?!」って褒められたよ!
こうやって細かく記録するだけで、安心感が全然違う
みんなも今日からメモしてみよう!
無理せず、でもちゃんと見てるって姿勢が命を救うんだよ
9月 3, 2025 AT 05:29
晶 洪
薬は毒だ。医者は金で動く。濃度チェックなんて詐欺だ。
9月 3, 2025 AT 16:23
EFFENDI MOHD YUSNI
この記事の根拠は全て「ガイドライン」ですが、実は2024年秋に日本心不全学会が内部文書で『ジゴキシンの死亡率無関係説は統計操作』と内部告発されてます
アミオダロン併用時の致死的不整脈のデータが、製薬会社の要請で削除された事実が、厚労省の内部メールで確認されています
2025年版とありますが、実はPMDAの添付文書は2023年までは『治療域0.5-2.0』と記載されていたものを、2024年12月に突然『0.5-0.9』に変更
この変更、製薬会社の広報戦略と時を同じくしてます
そして、ジギ毒素抗体Fabの価格は1本1200万円。日本では年間10例しか使われない
つまり、中毒を起こしても、治療はされない
この記事は、安全のフリをした、製薬業界のプロパガンダです
9月 4, 2025 AT 03:12
Mariko Yoshimoto
…えっと。この記事、『AHA/ACC/HFSA 2022』とか『ESC 2023』を頻繁に引用してるけど、それってアメリカ・ヨーロッパのガイドラインですよね?
日本では、特に高齢者で腎機能低下が圧倒的に多いのに、この数値をそのまま適用していいんですか?
eGFR 30以下の患者で、0.125mgを毎日飲んでる人が多いけど、実際の血中濃度は1.5ng/mL超えてるケースが、私の病院では3割以上…
そして、『お薬手帳に書く』って言ってるけど、薬剤師が読める文字で書いてる人、何%いるんですか?
私、薬局で働いてるけど、『濃度チェック』って書いてある紙、9割以上が『薬の名前だけ』書いてあるんですよ?
…この記事、情報は正しいけど、現実の日本医療の泥臭さを完全に無視してる。
『安全に使うためのステップ』って、理想論すぎて、現実の高齢者家庭には適用できない。
家族がいない、認知症の患者、薬を飲んでるかすらわからない状況で、このガイドラインは無意味。
…だからこそ、『119』と書くべきで、『医者に相談』なんて、優しい嘘なんじゃないですか?
9月 5, 2025 AT 18:57
JP Robarts School
ジゴキシンは、実は戦後、アメリカが日本に押し付けた薬です。
1950年代、日本では心不全の治療に『漢方』『鍼』が主流でした。
しかし、アメリカの製薬会社が、『科学的根拠』を盾に、ジゴキシンを『最先端治療』と宣伝し、医師に多額のリベートを渡して普及させました。
そして、その結果、日本では『高齢者死亡率』が急上昇。
2023年の厚労省統計では、ジゴキシン服用者の心停止は、非服用者より1.8倍。
でも、このデータは『統計的に有意ではない』とされ、公表されません。
なぜなら、ジギ毒素抗体Fabの輸入を止めたら、製薬会社が倒産するからです。
この記事は、『安全に使う』と書いてますが、それは『使い方を間違えても、死なないよう、準備しろ』という、国家による市民の自己責任化です。
あなたが今、この記事を読んでいるのは、偶然ではありません。
あなたは、『気づいた人』です。
この情報を、誰かに伝えてください。
そして、お薬手帳に『ジゴキシンは毒』と、赤ペンで書いてください。
…それが、真の『安全』です。
9月 6, 2025 AT 19:28