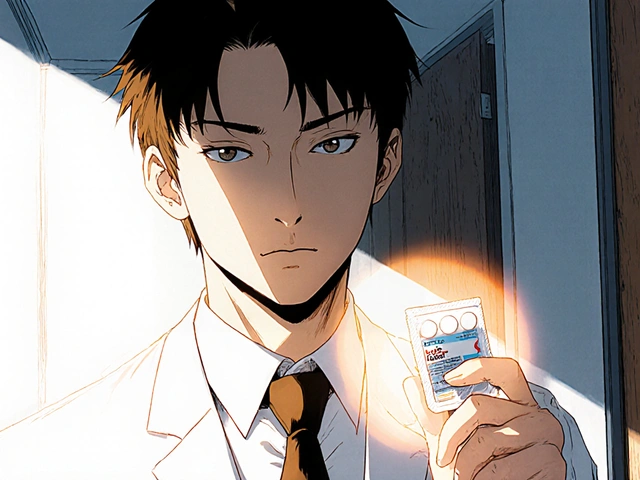細菌感染症に効く抗生物質:種類と働きの仕組み

- 三浦 梨沙
- 12 1月 2026
- 0 コメント
抗生物質は、細菌による感染症を治すために使われる薬です。風邪やインフルエンザには効かず、細菌だけに作用します。1928年にアレクサンダー・フレミングがペニシリンを発見してから、戦争中の傷口の感染症を救い、現代医療の基盤となりました。今では100種類以上が世界中で使われていますが、耐性菌の増加で、効かなくなる薬も増えています。
抗生物質はどのように細菌を倒すのか
抗生物質は、細菌の命を守る仕組みを狙って働きます。人間の細胞にはない部分を攻撃するので、体に大きなダメージを与えにくいのです。主に4つの方法で作用します。
まず、細菌の細胞壁を壊す方法です。細菌は、外側に硬い壁で自分を守っています。この壁がないと、中身が破裂して死んでしまいます。ペニシリンやセファロスポリンなどのβ-ラクタム系は、細胞壁の材料をつなぎ合わせる働きを妨げます。この薬の分子は、細菌が使う材料とそっくりなので、細菌が誤って取り込んでしまい、壁の構築を止めてしまうのです。これにより、細菌は水分を保てなくなり、膨れて破裂します。
次に、タンパク質の合成を止める方法です。細菌は、自分の体を作るためのタンパク質を毎日作り続けています。マクロライド系(エリスロマイシン、アズithロマイシン)やテトラサイクリン系(ドキシサイクリン)は、細菌のリボソームというタンパク質製造機に取り付いて、作業を止めます。アミノグリコシド系(ジェンタマイシン)は、タンパク質の設計図(mRNA)を読み間違わせて、壊れたタンパク質を作らせます。この方法は、細菌の成長を止める(細菌増殖阻止)効果が強く、感染が重いときによく使われます。
3つめは、DNAやRNAの複製を妨げる方法です。フルオロキノロン系(シプロフロキサシン、レボフロキサシン)は、細菌のDNAを巻き解くための酵素をブロックします。DNAが解けないと、細菌は自分を増やせません。この薬は、肺や骨、尿路など、体の奥深くまで届きやすいので、重い尿路感染や肺炎に使われます。ただし、かかとの痛みや神経障害のリスクがあるため、FDAは注意喚起を出しています。
最後に、葉酸の合成を止める方法です。葉酸は細菌がDNAを作るために必要です。スルホンアミド系(スルファメトキサゾール)は、葉酸を作る酵素を阻害します。しかし、耐性菌が多く、単独で使うことは減っています。代わりに、肺炎の一種であるPneumocystis jiroveciiの治療では、他の薬と組み合わせて使われます。
代表的な抗生物質のクラスと使い分け
抗生物質は、効く細菌の種類によって使い分ける必要があります。細菌は大きく分けて、グラム陽性菌とグラム陰性菌の2種類に分けられます。
ペニシリンやセファロスポリンは、グラム陽性菌(例:溶連菌)に強く、喉の痛みや皮膚の感染症の第一選択薬です。セファロスポリンは、世代によって効く範囲が広がります。第1世代は主にグラム陽性菌、第2世代は一部のグラム陰性菌にも効き、第3世代(セフトリアキソン)は大腸菌や緑膿菌までカバーします。第4世代のセフェピムは、さらに幅広く効きます。
テトラサイクリンは、マラリアやクラミジア、マイコプラズマといった「特殊な細菌」にも効きます。しかし、8歳以下の子どもには使えないのは、歯の色が茶色く変色するリスクがあるからです。また、日光に当たると皮膚が赤くただれる(光毒性)こともあり、外出時は日焼け止めが必要です。
マクロライド系は、ペニシリンアレルギーの人の代替薬としてよく使われます。アズithロマイシンは、1日1回で済むので、患者の飲み忘れが少なく、風邪の後で続く咳や軽い肺炎に有効です。
メトロニダゾールは、嫌気性菌(酸素がない場所で生きる細菌)に特化した薬です。歯周病や腹膜炎、腸内の感染に使われます。ただし、お酒を飲むと吐き気や頭痛が起きる「ディスルピラム反応」が7割の人に起こるので、治療中は絶対に飲酒を避けてください。
リネゾリドは、耐性菌に対して最後の切り札として使われる薬です。完全に人工的に作られた最初の抗生物質で、タンパク質合成の「スタート」をブロックします。MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)やVRE(バンコマイシン耐性腸球菌)に有効です。しかし、長く使うと貧血や神経障害が出るため、2週間以上は原則使われません。

なぜ抗生物質は効かなくなるのか
抗生物質は、使いすぎると効かなくなります。これは、細菌が進化して薬の攻撃を防ぐ仕組みを身に着けてしまうからです。
例えば、β-ラクタム系の薬は、細菌が作る「β-ラクタマーゼ」という酵素で分解されてしまいます。この酵素は、薬の分子を切断して無力化します。大腸菌や肺炎桿菌の多くが、この酵素を持つようになり、セファロスポリンやペニシリンが効かなくなっています。
フルオロキノロンも、耐性率が世界中で急上昇しています。WHOの2023年報告によると、大腸菌に対する耐性率が50%を超える国が72カ国にも及んでいます。これは、風邪で薬をもらった人が、症状が良くなったからと途中で飲むのをやめたり、動物の飼育で大量に使われたりしたことが原因です。
耐性菌が広がると、手術やがんの化学療法、早産の赤ちゃんの治療さえも危険になります。なぜなら、これらの治療では、感染を防ぐために抗生物質が必須だからです。
正しい使い方と注意点
抗生物質は、医師の診断がなければ飲んではいけません。風邪やインフルエンザに抗生物質を飲んでも、全く効果がありません。米国CDCのデータでは、外来患者の30%が不適切に抗生物質を処方されています。
正しく使うためには、以下のルールを守ってください:
- 医師が「細菌感染」と診断した場合だけ服用する
- 処方された量を、指示された日数すべて飲み切る(症状が良くなってもやめない)
- 他人に譲ったり、余った薬を保存したりしない
- 自己判断で市販薬を飲まない
最近では、プロカルシトニンという血液検査で、ウイルス感染と細菌感染を区別する方法が広がっています。この検査を使うと、抗生物質の不要な使用が23%減ったという研究もあります。

新しい抗生物質の開発と未来
耐性菌への対策として、新しい薬の開発が進んでいます。2019年にFDAが認可したセフィデロコールは、細菌が鉄を取ってくる仕組みを利用して、薬を体内に運び込む「スiderophore」という仕組みを使っています。これにより、これまで効かなかった耐性菌にも届くようになっています。
しかし、新薬の開発は非常に難しいです。開発にかかる費用は15億ドル以上ですが、売上は年間1700万ドル程度にとどまります。製薬会社は、がんの薬のように儲からないため、開発をやめてしまうのです。
イギリスでは、新しい抗生物質を「Netflixのように」年間固定料金で国が購入する「ネットフリックスモデル」の実験が始まっています。薬の使用量に関係なく、開発者に報酬を支払うことで、新しい薬を最後の切り札として保存しようとしています。
今後は、細菌のウイルス(バクテリオファージ)を使って感染症を治す「ファージ療法」も注目されています。2024年には、緑膿菌による中耳炎の臨床試験が第3相に入っています。
抗生物質と腸内細菌の関係
抗生物質は、病原菌だけを殺すわけではありません。腸の中にいる善玉菌も一緒に殺してしまうのです。
ハーバード大学のマーティン・ブラザー教授は、広範囲の抗生物質を1回使うと、腸内細菌の多様性が最大12か月も回復しないと指摘しています。その結果、大腸菌の一種であるClostridioides difficileが増えて、重い下痢や腸炎を起こすリスクが17倍にもなるのです。
そのため、できるだけ「狭い範囲」の抗生物質(細菌の種類を絞って効く薬)を使うことが、今後の医療の鍵になります。例えば、溶連菌の喉の感染症なら、ペニシリンだけで十分です。わざわざ広範囲の薬を使う必要はありません。
日本でも、医療現場では「適正使用」の取り組みが進んでいます。病院では、感染症専門医が抗生物質の処方をチェックするシステムが導入され始めています。一人ひとりが正しい知識を持ち、薬を大切に使うことが、未来の医療を守ります。